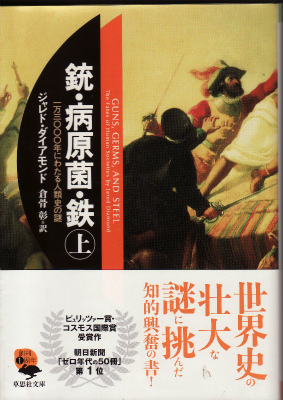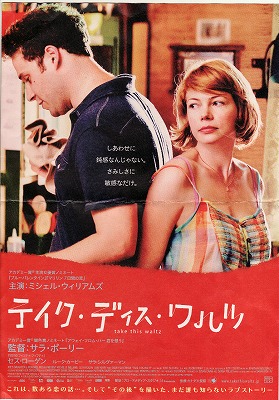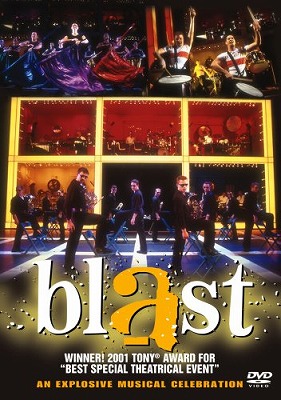ハンググライダーの事故で全身麻痺になってしまった中年の大富豪のフィリップは、ノーブル、インテリであるが、妻にも先立たれ少々ひねくれている。介護者の同情や腫れ物に触るような扱いはには皮肉な態度を取るため誰も長続きしない。スラム出身の黒人青年ドリス(オマール・シー)は生活保護の申請に必要な不採用通知を目当てに面接にきた不届き者だったが、何故かフィリップは彼を採用することになる。ドリスは親不孝、自身も身内も犯罪者、本人はその日暮らしと、フィリップとは真逆の人生を歩んできたが、階級社会で、さらに異人種、異教徒でお互い接点があり得なかったために、かえって気楽な労使関係から、思いやりを持てる友情に発展出来たのかも。「最高に人生の見つけ方」でも富豪白人ジャックニコルソンと町工場黒人フリーマンのコンビだった。貧富の落差は大きいほどその後の友情はおとぎ話で観る者には楽しい。日本で育った私にはにはそれほど心温まるような話には思えませんでした。
ハンググライダーの事故で全身麻痺になってしまった中年の大富豪のフィリップは、ノーブル、インテリであるが、妻にも先立たれ少々ひねくれている。介護者の同情や腫れ物に触るような扱いはには皮肉な態度を取るため誰も長続きしない。スラム出身の黒人青年ドリス(オマール・シー)は生活保護の申請に必要な不採用通知を目当てに面接にきた不届き者だったが、何故かフィリップは彼を採用することになる。ドリスは親不孝、自身も身内も犯罪者、本人はその日暮らしと、フィリップとは真逆の人生を歩んできたが、階級社会で、さらに異人種、異教徒でお互い接点があり得なかったために、かえって気楽な労使関係から、思いやりを持てる友情に発展出来たのかも。「最高に人生の見つけ方」でも富豪白人ジャックニコルソンと町工場黒人フリーマンのコンビだった。貧富の落差は大きいほどその後の友情はおとぎ話で観る者には楽しい。日本で育った私にはにはそれほど心温まるような話には思えませんでした。
最後にフィリップは結婚したのかな?