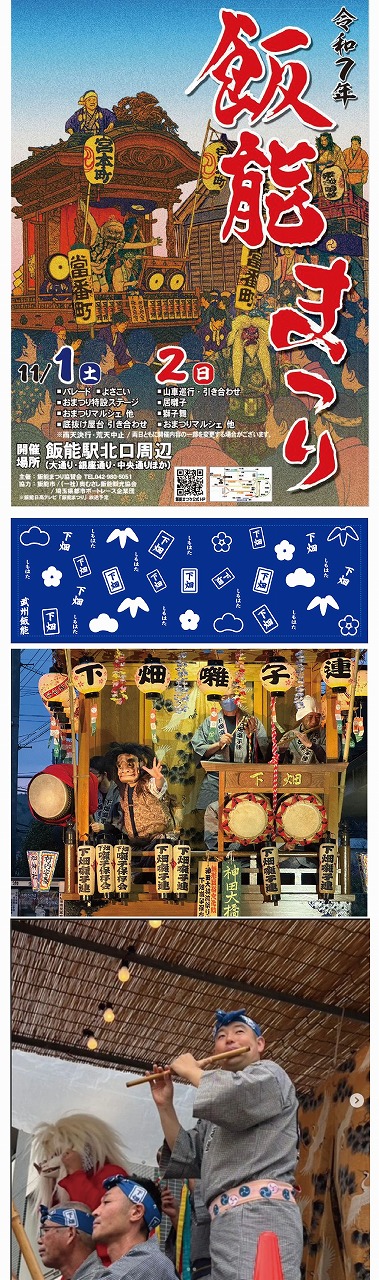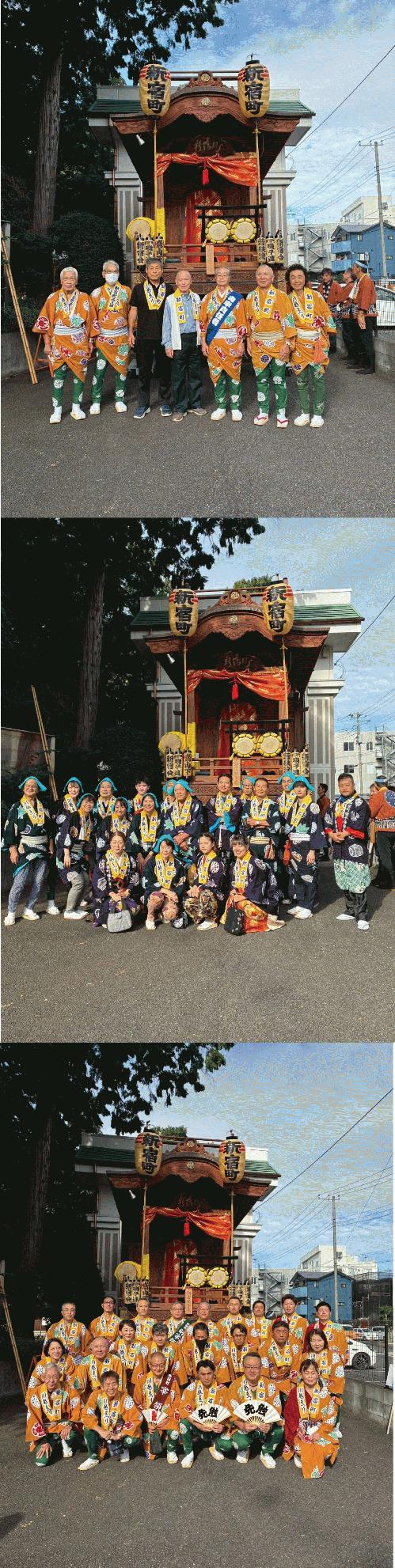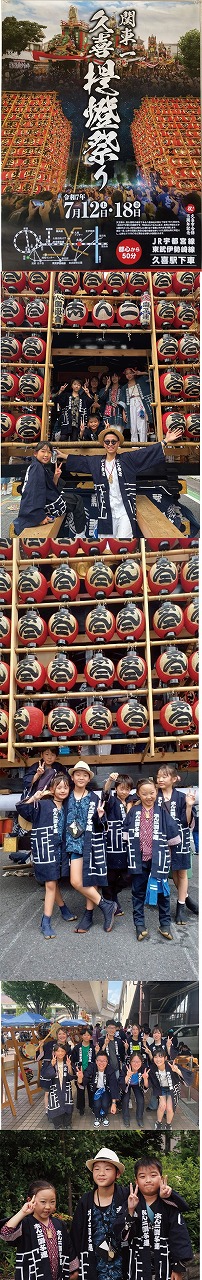長宮氷川神社は、埼玉県ふじみ野市長宮にある神社です。地元では「長宮氷川神社」と呼ばれ、ふじみ野市上福岡地区の総鎮守として地域の方々に大切にされています。
今から約1000年前の長徳元年(995年)、北面武士の星野信秀が、出雲大社(当時の杵築大社)からご神霊を勧請したのが始まりと伝えられています。
「長宮」という名前は、長い参道が続く様子に由来するという説や、中氷川神社(旧称:長宮明神社)に由来するという説があります。明治時代には旧福岡村の村社にも指定されています。
長宮氷川神社のご祭神は、建速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)、大己貴命(おおなむちのみこと)です。このうち建速須佐之男命と奇稲田姫命は、八岐大蛇から奇稲田姫命を救った後に結婚したことから、縁結びの神様として信仰を集めています。
のぼり 100㎝*10m 帆布